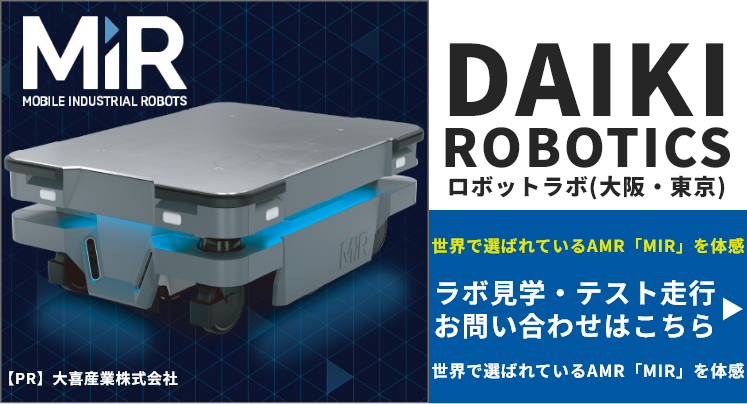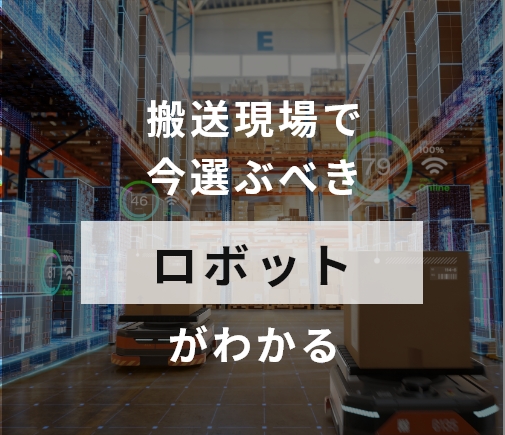知らないとリスクが増加?AMR・AGVに関する2つの規格「ISO3691-4」と安全対策を解説 | 搬送ロボットガイド
AMR
知らないとリスクが増加?AMR・AGVに関する2つの規格「ISO3691-4」と安全対策を解説
公開:2023.10.02 更新:2026.01.29
「ISO3691-4」という国際規格は、自動運搬ロボット(AMR・AGV)の安全運用に不可欠で、無人搬送車の安全性を確保し、製造業者とオペレーターに明確な手順を提供するガイドラインです。
また、AMRの導入にはリスクアセスメントが必要で、機器制限、危険源特定、リスク評価が含まれます。これらを実施することで、無人搬送車の安全性と効率性が向上します。
この記事ではISO3691-4について解説し、必要な安全項目やリスクアセスメントについて紹介していきます。
目次
ISO 3691-4とは?
物流や工場で使われる「無人搬送車(AGVやAMR)」は、人が運転しなくても自動で荷物を運ぶ頼もしい存在です。けれども、機械が自動で動く以上、事故を防ぐためのルール作りが欠かせません。そこで重要になるのが国際規格です。
ここでは、その中心となるISO 3691-4という規格と、関連する3つの規格ISO 13849-1、IEC 61508、EN 1175のつながりを、一般の方にもわかるように整理します。
◇AGVやAMRの安全性に関する国際規格
◇ISO 3691-4で定めている内容
ISO 3691-4は、AGVやAMRが人と同じ空間で安全に走行・作業するための国際安全規格です。単なる注意事項ではなく、設計・制御・運用までを含めた総合的な安全要求が定められている点が大きな特徴です。
規格では、AGV・AMRの安全性を確保するために、以下のような項目が体系的に整理されています。
- 走行中の速度制御や減速ルール
- ブレーキ性能および停止性能
- 人や障害物の検知方法と安全距離
- 非常停止装置の構造と確実な動作
- バッテリーの取り扱いおよび充電時の安全性
特にブレーキ性能については重要度が高く、「どの条件で減速・停止すべきか」「制御系に異常が発生した場合でも安全に停止できるか」といった観点から、冗長性や信頼性が求められています。単にブレーキが搭載されているだけでなく、故障時でも危険な状態にならない設計であることが前提です。
人を検知する機能についても、センサーの有無だけでは不十分とされています。
検知距離、反応時間、停止までに必要な安全距離などが具体的に定義されており、走行速度や使用環境に応じた安全設計が求められます。これにより、人が突然接近した場合でも衝突を回避できる仕組みを確保します。
また、AGVやAMRは無人で充電ステーションへ移動・充電する運用が多いため、バッテリー関連の安全性も重要なポイントです。
感電や火災を防ぐための構造、誤作動を防止する制御、充電中の異常検知機能などについても、ISO 3691-4の中で明確に触れられています。
総合するとISO 3691-4は、
「自動で走行する搬送ロボットが、人や設備に危害を与えないための共通ルールを体系化した規格」
といえます。単なるルールの羅列ではなく、リスクを前提に、どのように低減するかを設計思想として示している点が特徴です。
AGV・AMRを選定・導入する際には、ISO 3691-4への適合状況を確認することが、安全な運用と長期安定稼働につながる重要な判断材料となります。
◇ISO 3691-4の適用範囲
ISO 3691-4の適用範囲は、無人で走行する産業用トラック全般に及びます。具体的には、あらかじめ決められたルートを走行するAGV(無人搬送車)だけでなく、周囲の状況を認識しながら自律的に走行するAMR(自律移動ロボット)も対象に含まれます。
一方で、人が搭乗して操作するフォークリフトや、屋外専用の特殊車両などについては、ISO 3691-4の直接的な適用対象外となるケースがあります。
この規格の大きな特徴は、「機械そのもの」だけでなく「使用される環境」まで考慮している点です。
例えば、作業者が頻繁に行き交うエリアで使用されるのか、立ち入りが制限された専用エリアで使用されるのかによって、求められる安全対策のレベルは大きく異なります。そのため、単に「規格に適合した機体を導入すればよい」という考え方では不十分とされています。
導入時には、
- 機体がISO 3691-4に適合しているか
- 実際の運用環境においてリスク評価が適切に行われているか
といった点をセットで確認することが重要です。特に、人とロボットが同じ空間で稼働する現場では、運用方法や動線設計まで含めた安全対策が求められます。
このようにISO 3691-4は、「どの機械に適用されるか」を単純に線引きする規格ではありません。
使用条件や運用方法まで含めて安全を捉える枠組みを提供しており、現場ごとのリスクを前提に、安全な自動化を実現するための基準として位置づけられています。
◇ISO 3691-4と関連する国際規格
ISO 3691-4は単独で完結する規格ではなく、複数の国際規格と連携することで、安全設計の全体像を構成しています。ここでは、特に関係が深い規格について説明します。
ISO 13849-1
ISO 3691-4の中には「ブレーキ装置はこれくらいの安全レベルが必要」というように、安全度を数値で表す仕組みが使われています。この数値の決め方を教えてくれるのがISO 13849-1です。
ISO 13849-1は「機械を制御する仕組みを、どのくらい信頼できる設計にすればいいか」を示す規格です。例えば、1つの部品が壊れても別の仕組みで補えるようにしたり、部品の寿命を見積もって壊れる確率を下げたりといった工夫を求めています。
つまり、ISO 3691-4は「無人搬送車に必要な安全対策のリスト」を示し、その裏側でISO 13849-1が「その安全対策をどう設計すればよいか」を支える関係になっています。
IEC 61508
もう一つよく出てくるのがIEC 61508です。これは産業分野全体で使われる「機能安全の基本ルール」です。医療機器でも鉄道でも、自動化装置に使われる電子システムはこの考え方に従っています。
IEC 61508は「安全関連システム」をどのくらいの信頼性で作るべきかを、SIL(Safety Integrity Level)という指標で表します。ISO 13849-1が「機械制御向けのルールブック」だとすれば、IEC 61508はもっと広い分野をカバーする「基礎教科書」です。
ISO 3691-4の中でも、センサーやソフトウェアのように複雑な装置を扱う部分では、このIEC 61508の考え方を取り入れて設計を進めることが推奨されています。
EN 1175
最後に紹介するのがEN 1175です。これはヨーロッパで定められた規格で、産業用トラックの「電気系統の安全」を細かく決めています。
例えば、配線や電子部品が故障したときに火災や感電の危険がないか、緊急時に確実に電源を切れるか、といった観点がカバーされています。ISO 3691-4が「車両全体の安全ルール」であるのに対し、EN 1175は「中に使われる電気部品の安全ルール」と考えるとわかりやすいでしょう。
【あわせて読みたい】
▼ロボットがもっと安全に!AMRの安全管理と活用事例をチェック
「JISD6802」とは?

JISD6802は、日本国内において無人搬送車(AGV)や自律走行搬送ロボット(AMR)を安全に運用するために定められた工業規格です。日本国内でAGV・AMRを導入・運用する際の基本的な安全指針として、多くの現場で参照されています。
◇ISO3691-4に準拠した日本国内の安全規格
JISD6802は、国際規格であるISO 3691-4の考え方をベースに、日本向けに整理された安全規格です。
ISO 3691-4は、AGVやAMRなどの無人で走行する産業用トラックに関する安全要求事項を包括的に定めた国際規格で、欧州ではCEマーキングの判断基準としても重視されています。
一方、日本国内では、
- 関連法令の位置づけ
- 安全に対する考え方
- 現場運用の慣習
などが海外と異なる部分も少なくありません。JISD6802は、こうした日本独自の事情を踏まえたうえで、ISO 3691-4の安全思想や技術要件を反映した規格として位置づけられています。
具体的には、
- 人検知・障害物検知の考え方
- 減速・停止のタイミング
- 非常停止装置の設計思想
などが、ISO規格と整合する形で整理されています。そのため、JISD6802に対応したAGV・AMRは、国際的な安全基準に沿った設計がなされていると判断しやすい点が特徴です。
また、国内メーカーやシステムインテグレーターにとっては、日本語で整理されたJIS規格を参照できることにより、設計や導入判断がしやすくなるという利点もあります。結果として、現場の安全確保と自動化推進の両立を支える規格となっています。
◇JISD6802の対象範囲
JISD6802の対象となるのは、人が搭乗せずに自動または自律的に走行する搬送車両です。
具体的には、
- 決められた経路を走行するAGV
- 周囲の状況を認識しながら走行経路を判断するAMR
が含まれ、工場・倉庫・物流センターなどでの荷物搬送用途が想定されています。
対象範囲には、車両本体の構造や走行機構だけでなく、
- 人検知・障害物検知用のセンサー類
- 制御システムや安全ロジック
- 検知後の減速・停止動作
- 警告表示や警報音の出し方
といった安全機能全体が含まれます。
一方で、
- 人が操作するフォークリフト
- 屋外専用の特殊車両
- 用途が大きく異なるロボット
については、別の規格や基準が適用される場合があります。そのため、導入検討時には、使用予定の機器がJISD6802の対象に含まれるかを事前に確認することが重要です。
また、JISD6802は、「機械単体の安全性」だけでなく「使用環境との関係」も重視しています。
人が頻繁に通行するエリアと、立ち入り制限があるエリアとでは、求められる安全対策のレベルが異なるためです。
このため、規格への適合そのものがゴールではなく、実際の運用環境に即したリスク評価と安全対策の実施が前提となります。
JISD6802は、日本国内におけるAGV・AMRの安全運用を支える基盤的な指針として、設計者・導入企業・運用担当者のいずれにとっても重要な役割を果たしています。
【あわせて読みたい】
▼AMRロボットの一般的な速度は?高速AMRロボットの魅力と安全性
自動運搬ロボット(AMR・AGV)の安全対策|リスクアセスメント
AMRの安全性確保は、JISD6802「無人搬送車システムー安全規則」への準拠が不可欠です。そのため、AMRを導入する際にはリスクアセスメントが重要な役割を果たします。
◇AMRの導入で想定されるリスク
AMR導入時に安全規格や運用条件を十分に考慮しない場合、重大事故につながるリスクが高まります。
例えば、規格で求められる安全構造を満たしていないAMRを導入してしまうと、荷物の落下による押し潰し事故や、足を轢かれるといった深刻な人身事故が発生するおそれがあります。
また、想定している運用に必要な安全機能を備えていないAMRを選定した場合、人との衝突や挟まれ事故など、回避できたはずの事故が起こるリスクも高くなります。
さらに、AMRの走行ルートや速度が現場環境に適切に設定されていないと、通路や壁際で人が挟まれる、交差点で人と衝突するといった事故につながりやすくなります。
加えて、飛び出しなどの残留リスクに対する有効な対策を講じていない場合、最終的に人身事故を防げない可能性も残ります。
具体的な重大事故の例
- 人検知用センサに安全用途ではない汎用センサを使用しており、故障時に人を検知できず衝突
- AMRに作業者が足を轢かれて骨折
- AMRから搬送物が落下し、近くにいた作業者が負傷
- 残留リスクである人の飛び出しに対応できず、AMRと衝突
事故が起きた場合に生じる影響
・事故や怪我のリスク増加
安全対策が不十分なまま運用すると、人の注意や判断に依存した運用になりやすく、結果として事故や怪我の発生リスクが高まります。
・生産性の低下とコスト増加
事故が発生すると業務停止による機会損失が生じやすくなります。また、損傷した設備やAMR本体の修理・交換コストも発生し、想定外の負担につながります。
・法的責任と企業リスク
労働安全衛生法では、リスクアセスメントに基づいた設備安全化が求められています。そのため、事故が発生した場合、企業側が法的責任を問われるリスクが高まります。
場合によっては、刑事罰や罰金、営業停止、訴訟といった事態に発展する可能性も否定できません。結果として、企業の信用や評判の失墜につながるリスクも大きくなります。
また、ISO 3691-4を十分に理解しないままAMRを導入した場合、安全機能の設計思想やリスク低減の考え方が不足した状態で運用が始まってしまう可能性があります。その結果、万が一事故が発生した際に、企業側の安全配慮義務や管理責任が問われるリスクも高まります。
◇AMR運用におけるリスクアセスメントの流れ
AMRを安全かつ安定して運用するためには、導入前後を通じてリスクアセスメントを体系的に実施することが欠かせません。リスクアセスメントは、単に危険を洗い出すだけでなく、想定される事故を未然に防ぎ、運用中のトラブルや停止を減らすための重要なプロセスです。
こちらでは、AMR運用において押さえておくべきリスクアセスメントの基本的な流れについて解説します。
1.機器類の制限の決定
AMRを導入する際には、AMRだけでなく周辺機器についても考慮する必要があります。各機器の使用範囲、設置環境、稼働時間などの仕様を検討し、決定する必要があります。これにはAMR1台ごとの稼働範囲や走行速度なども含まれます。
2.危険源の特定
次に、AMR導入時にどのような危険があるかを考えます。AMRの走行中における危険源とその発生状況を想定し、可能なリスクを特定します。積載物の落下や衝突など、あらゆる角度から検証が必要です。
3.リスク見積もり
危険源が特定されたら、それぞれのリスクについて見積もりを行います。リスク見積もりは、リスクの重篤度、発生可能性、危険性の頻度に基づいて評価されます。これにより、客観的なリスク評価が可能となります。
4.リスク評価
最終的に、リスク見積もりの結果をもとに、AMR導入時のリスクを評価します。
AMRの導入においては、リスク評価が高い場合、安全対策を講じなければなりません。事前の対策が後で問題を引き起こす可能性もあるため、安全性を確保するためのリスクアセスメントは非常に重要です。
【あわせて読みたい】
▼AMRロボット導入の安全対策は必須!具体的方法や導入の注意点
ISO 3691-4とセーフティ技術の実際
◇無人搬送車を守る“目”-LiDARと3Dカメラ
無人搬送車(AGVやAMR)が安全に走るために欠かせないのが「周囲を認識する目」です。その代表例がLiDAR(ライダー)と3Dカメラです。
LiDARはレーザー光を高速で照射し、その反射を測定して周囲の障害物までの距離を正確に計算します。非常に高精度で、動いている人や物体も瞬時に検知できるため、ISO 3691-4で求められる「人に接近したら減速・停止する」機能に直結します。一般的にLiDARを安全システムとして使う場合は、PL d以上(ISO 13849-1の要求水準)に対応可能です。これは「高い信頼性を持ち、一つの故障が起きても重大事故につながらない」レベルです。
3Dカメラは、映像から立体的に空間を捉える技術で、障害物だけでなく「人か物体か」をある程度識別できるのが強みです。AIとの組み合わせでさらに賢く使える一方、光の条件に弱かったり、確実な検知には冗長設計が必要です。そのため、単独ではPL c程度の適用が一般的で、より高いPLを達成するにはLiDARなどと組み合わせて冗長性を確保します。
つまり、LiDARは「正確で頼もしい目」、3Dカメラは「状況を理解する柔軟な目」として役割分担し、安全を強化しているのです。
◇周囲を常に監視する守護者-セーフティレーザースキャナ
ISO 3691-4の実装例で特に有名なのがセーフティレーザースキャナです。これはLiDARの安全版とも言えるもので、安全規格に準拠して設計されているため、PL d〜eといった非常に高い安全性能を実現可能です。
セーフティレーザースキャナは、AGVやAMRの前方や側面に取り付けられ、扇形の監視領域を常にスキャンします。人や障害物が侵入すると、瞬時に警告領域から停止領域へと切り替わり、ロボットを安全に制御します。
たとえば、警告ゾーンでは速度を自動的に落とし、危険ゾーンに侵入された瞬間に完全停止する、といった多段階制御が可能です。この柔軟かつ強力な機能は、工場や倉庫で「人と機械が同じ空間を共有する」場面において大きな安心感を生み出しています。
◇“最後の砦”-非常停止ボタンとアラーム
どれほど賢いセンサーを積んでいても、人間がすぐに止められる仕組みは必須です。ここで活躍するのが非常停止ボタン(E-Stop)です。
非常停止ボタンは、赤くて大きな押しボタンとしてロボットや周囲の壁に配置され、誰でも瞬時に操作できるようになっています。安全規格上、非常停止回路はPL eにまで設計されることが多く、「最も高い安全性」を保証します。つまり、一つの故障が起きても必ず安全に停止するよう二重三重に作られています。
さらに、アラーム(音や光の警告装置)も重要な要素です。ロボットが近づいてくるときに「ピッピッ」と音を出したり、回転灯を点滅させることで、作業員に直感的な注意を促します。これ自体はPL評価の対象というよりは「付加的な安全策」ですが、事故防止において心理的な効果は絶大です。安全規格では「警告は安全機能の代替にはならない」とされますが、実運用では欠かせない存在になっています。
◇技術と規格が織りなす多重の安全網
ここまで見てきたように、ISO 3691-4に基づく無人搬送車の安全設計は、一つの技術に頼るのではなく、複数の仕組みを重ねることで成り立っています。
- LiDAR:高精度で信頼性の高い障害物検知。PL d対応可。
- 3Dカメラ:状況を理解する柔軟な目。PL c相当、組み合わせで強化。
- セーフティレーザースキャナ:安全規格準拠でPL d〜e。人との協働環境で安心。
- 非常停止ボタン:人が介入できる最後の砦。PL eで最高レベル。
- アラーム:注意喚起の補助、安全意識を高める心理的効果。
このように、ISO 3691-4は「どの安全機能をどのレベルで実装すべきか」を明確に示し、それぞれの技術がどのPLレベルに対応できるかを整理することで、設計者や現場担当者が迷わずに導入判断を下せるようになっています。
安全の世界では「過剰」なくらい慎重な設計が求められます。だからこそ、センサーやカメラが常に周囲を監視し、レーザースキャナが守りを固め、人の手で押せる非常停止ボタンが最後の砦となり、アラームが注意を促す――この多重防御の考え方こそが、未来の安全な自動化現場を支えていくのです。
ISO 3691-4へ準拠したAMR

工場や物流現場で人と協働しながらAMRを運用する場合、ISO 3691-4への準拠は重要な判断基準となります。ISO 3691-4は、AGV・AMRといった無人搬送車が安全に走行するための国際規格で、人検知、減速・停止制御、非常停止などの安全要件が体系的に定められています。
この規格に対応したAMRを選定することで、現場の安全性を確保しつつ、自動化を無理なく進めやすくなります。
◇MiR|MiR250・MiR600

MiR250およびMiR600は、デンマークのMiR(Mobile Industrial Robots)社が開発したAMRで、ISO 3691-4に準拠した安全設計が特徴です。高精度レーザースキャナにより人や障害物を検知し、状況に応じて自動で減速・停止を行います。
MiR250は小型で取り回しが良く、中量物搬送を中心に、既存設備が多い工場や通路幅の限られた現場でも柔軟に運用できます。一方、MiR600は最大600kgまでの重量物に対応し、物流倉庫や生産ライン間の長距離搬送で活躍します。
安全機能と拡張性のバランスが良く、人との協働を前提とした現場で多く採用されているAMRです。
◇オムロン|MD-650

オムロン株式会社のMD-650は、日本の製造業や物流現場の運用実態を踏まえて設計されたAMRです。ISO 3691-4に基づく安全要件を満たし、複数のセンサーを組み合わせた冗長構成により高い安全性を確保しています。
人や障害物を検知すると即座に速度制御や停止を行うため、人の往来が多いエリアでも安心して導入できます。また、同社が持つ制御機器や生産管理システムとの親和性が高く、既存の自動化設備と連携しやすい点も特徴です。
安全性とシステム統合のしやすさを重視する企業に適したAMRといえます。
◇つばき|AMRシリーズ

つばきのAMRシリーズは、搬送機器メーカーとしての長年の知見を活かした設計が特長です。ISO 3691-4への準拠を前提に、人検知、減速制御、非常停止といった安全機能を標準装備しています。
用途や現場環境に応じて複数のモデルが用意されており、部品搬送から完成品の移動まで幅広い工程に対応可能です。堅牢性と安定稼働を重視した構造のため、製造現場での長時間運用にも向いています。
安全規格への対応と実用性の両立を重視したAMRとして評価されています。
◇テクトレ|月光AMR

月光AMRは、AI技術を活用した自律走行性能とISO 3691-4への対応を両立したAMRです。人や障害物の動きをリアルタイムで認識し、周囲の状況に応じて走行判断を行うため、人と同じ空間での協働作業にも適しています。
比較的コンパクトな設計ながら、柔軟なルート設定や拡張性を備えている点も特徴です。
安全性と先進性の両方を重視したい現場で注目されているAMRといえるでしょう。
ISO 3691-4をより理解するには
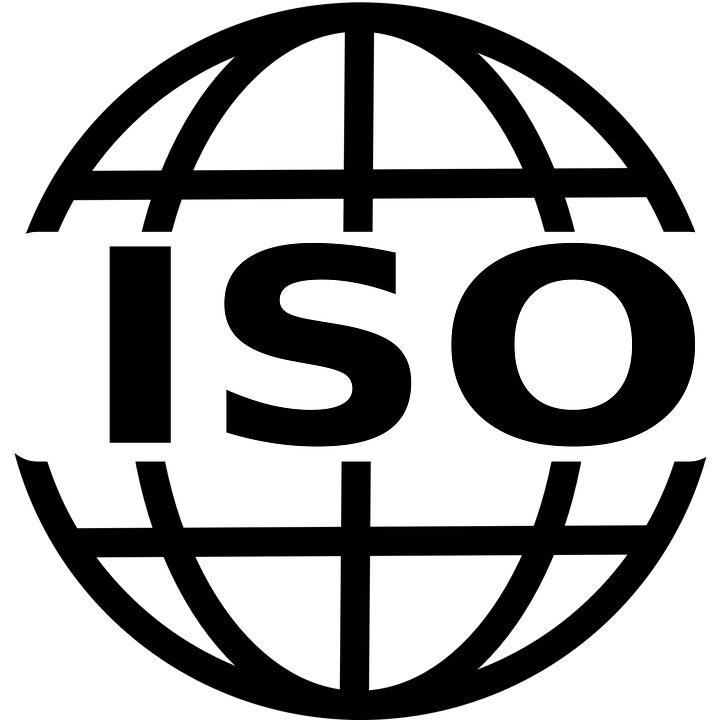
ISO 3691-4は、AMRやAGVを安全に導入・運用するための重要な国際規格ですが、条文を読むだけでは実務にどう落とし込めばよいか分かりにくい側面があります。現場で適切に活用するには、規格の背景や考え方を理解したうえで、導入プロセスやリスクアセスメントと結び付けて学ぶことが重要です。
そこで有効となるのが、セミナーの受講や専門支援サービスの活用です。
◇セミナーを受講
ISO 3691-4を理解する第一歩として、専門セミナーの受講は非常に有効です。特に、リスクアセスメントを実施する前に受講しておくことで、危険源の洗い出しや評価方法を正しく整理しやすくなります。
たとえば大喜産業株式会社の「AMRアカデミー(ベーシック)」では、AMRの基礎知識から安全規格の考え方までを体系的に学べます。
講座では、最新のAMR実機を使用した操作トレーニングも行われるため、座学だけでなく、実際の運用をイメージしながら理解を深められる点が特徴です。これにより、AMR導入後に必要となる基本操作や運用ノウハウを効率よく習得できます。
このセミナーは、
- AMRの導入を検討しているものの、基礎知識や操作方法が分からない方
- 情報収集段階にあり、機種や方式の選択肢が多くて判断に迷っている方
- 安全面の知識や運用ノウハウに不安があり、導入後の運用を具体的にイメージできていない方
といった課題を抱える担当者に適しています。AMR導入の初期段階から、安全性と実運用の両面を理解したい場合に有効な学習機会といえるでしょう。
◇対応支援サービスを活用
ISO 3691-4への対応を進めるうえでは、専門の対応支援サービスを活用する方法も有効です。規格への適合には、リスクアセスメントの実施、安全機能の確認、運用ルールの整備など、専門的な知識と実務経験が求められます。
これらをすべて自社だけで対応することが難しい場合、第三者による支援を受けることで、対策の抜けや漏れを防ぎながら進めやすくなります。対応支援サービスでは、規格要求事項の整理、現場状況の確認、必要な安全対策の提案などが行われ、ISO 3691-4に沿った安全設計を効率的に構築できます。
また、導入後の説明責任や監査対応を見据えた整理ができる点もメリットです。特定のメーカーに依存しない中立的な立場で助言を受けられるため、複数のAMRやAGVを導入する現場にとっても活用しやすい手段といえるでしょう。
AMRの導入を検討するならおすすめ国内業者3選
◇大喜産業株式会社

大喜産業株式会社は、日本のモノづくりを支える機械専門商社です。主に「ロボティクス事業」「伝動機器事業」「産業機器事業」「マテハン/設備機器事業」の4分野で事業展開しており、多様な産業へソリューションを提供しています。
特にロボティクス事業では、人と共存する協働ロボットの導入支援に注力し、自社オリジナルのパレタイズロボットや、OnRobotの自動化プラットフォーム「D:PLOY」を活用した簡単かつ柔軟なシステムを開発。顧客ごとに最適なモデル選定や提案を行うほか、自律移動型ロボット(AMR)の「MiR」や、工場・倉庫向けのロジスティクス最適化ソリューションも展開しています。
また、産業用ロボットの長年の実績とノウハウを活かし、導入後のサポートにも強みを持っています。
| 会社名 | 大喜産業株式会社 |
| 営業本部 | <住所> 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-5-9 <電話番号> 06-6541-1987 |
| 営業本部東京オフィス | <住所> 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア4F <電話番号> 03-5219-1463 |
| 大阪支店 | <住所> 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-5-9 <電話番号> 06-6532-0751 |
| 東京支店 | <住所> 〒333-0815 埼玉県川口市北原台3-2-21 <電話番号> 048-297-1388 |
| 東京支店つくばオフィス | <住所> 〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-5-7 ダイワロイネットホテルつくば2F <電話番号> 029-817-4844 |
| 名古屋支店 | <住所> 〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町416 <電話番号> 052-505-8201 |
| 東大阪支店 | <住所> 〒581-0861 大阪府八尾市東町4-1 <電話番号> 072-997-0123 |
| 京滋支店 | <住所> 〒520-3047 滋賀県栗東市手原3-2-3 <電話番号> 077-553-6155 |
| 四国支店 | <住所> 〒761-0301 香川県高松市林町2554-1 <電話番号> 087-868-4511 |
| 九州支店 | <住所> 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下2-4-7 <電話番号> 092-441-0198 |
| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |
| 公式ホームページ | https://www.daiki-sangyo.co.jp/ |
人材不足や現場の効率向上に貢献し、現場の課題解決と未来志向のモノづくりを支える存在です。
大喜産業株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼MiR社の魅力的なMiR製品とその販売代理店・大喜産業とは
さらに詳しい情報は公式ホームページでも確認できます。ぜひチェックしてみてください。
◇アルテック株式会社

アルテック株式会社は1976年創業の産業機械専門商社で、印刷・包装機械だけでなく、物流効率化の支援を手掛けています。
同社はカナダ・Clearpath Robotics社(OTTO Motors)の自律走行型搬送ロボット(AMR)「OTTO」シリーズの日本国内販売代理店であり、2017年から協業を開始。OTTOは磁気テープなどの敷設無しで人と同じ空間を自律走行し、工場や倉庫の省人化、マテリアルハンドリングの自動化を実現します。
用途や可搬重量に応じ複数モデル・アタッチメントが用意されている他、同社独自の管理システム「フリートマネージャー」を活用し、ロボット導入現場の運用最適化や外部システム連携も支援。神奈川県のロボティクスセンターでは実機見学も可能。
| 会社名 | アルテック株式会社 |
| 所在地 | 〒104-0042 東京都中央区入船2-1-1 住友入船ビル2F |
| 電話番号 | 03-5542-6760 |
| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |
| 公式ホームページ | https://smart-logistics.altech.jp/amr/otto/ |
アルテックは単なる販売に留まらず、コンサルティングやアフターサポートも含めたトータルソリューションを提供し、顧客のグローバル競争力強化に貢献しています。
アルテック株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼OTTO MortorsのAMRの特徴と可能性!日本での普及が期待される理由
◇ラピュタロボティクス株式会社

ラピュタロボティクス株式会社は、チューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発の技術系ベンチャー企業で、「ロボットを便利で身近に」をビジョンに掲げています。
世界30か国以上から集まった優秀なエンジニアや営業・カスタマーサクセスチームが連携し、最先端の制御技術とAIを活用したクラウドロボティクスプラットフォーム「rapyuta.io」や物流自動化ロボットの開発・導入・運用支援を展開しています。
主力製品のピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR」は、自律移動やAIによる最短ルート提案でスタッフの歩行距離を削減し、生産性向上と作業負荷軽減を実現します。
| 会社名 | ラピュタロボティクス株式会社 |
| 所在地 | 〒135-0023 東京都江東区平野4-10-5 |
| 電話番号 | 03-3639-4911 |
| 営業時間 | 公式サイトに記載なし |
| 公式ホームページ | https://www.rapyuta-robotics.com/ja/solutions-pa-amr/ |
2023年度グッドデザイン賞受賞など評価が高く、既存現場でも導入しやすく、人的作業との協働による現場改善やピッキングミス削減、ハンズフリーな運搬業務を可能とする最新物流ソリューションを提供しています。
ラピュタロボティクス株式会社の口コミ評判記事はこちら!
▼ラピュタロボティクスのAMRで生産性アップ!導入事例を紹介
まとめ

国際規格「ISO3691-4」は、AGVやAMRなどの無人搬送車の安全運用に必要な規格です。この規格は、無人搬送車とその運用システムにおける安全対策の包括的なガイドラインを提供し、迅速な安全策の策定を可能にします。
また、リスクアセスメントを行うことも重要で、機器の制限、危険源の特定、リスク評価などのステップを追うことで、AMRの導入時に安全性を確保できます。この規格とリスクアセスメントを遵守することで、無人搬送車の安全性と効率性を最大化できます。
この記事を読んでいる人におすすめ
▼AMRの利用には安全規格への準拠が不可欠!導入によるメリットや注意点について解説
▼【2025年最新版】失敗しないフリートマネジメントシステム導入で加速するAMRの生産性向上
▼ロボットの安定稼働を実現するメンテナンスの種類と手法とは?