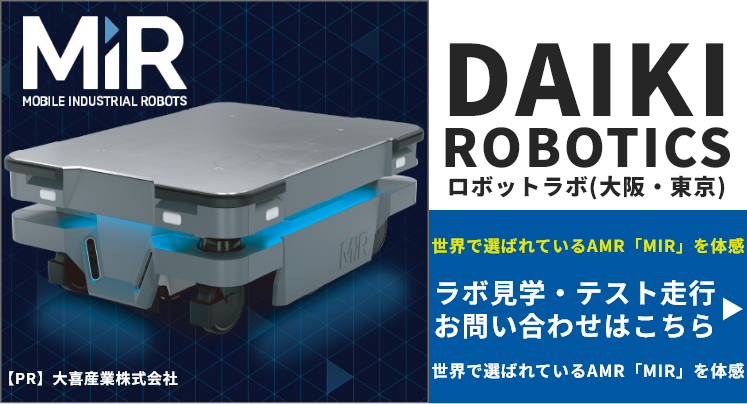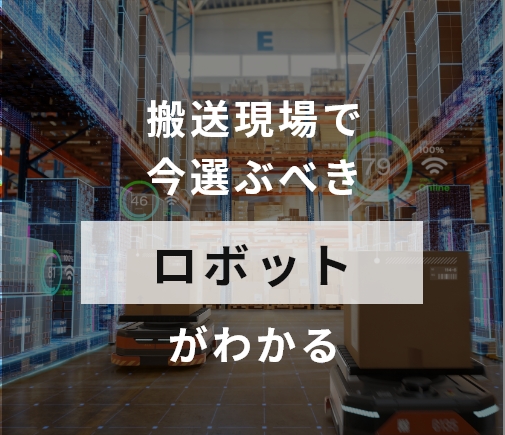搬送ロボットの種類ごとの活用シーンと普及が進むAMRについて | 搬送ロボットガイド
AMR
搬送ロボットの種類ごとの活用シーンと普及が進むAMRについて
公開:2023.09.27 更新:2024.10.07
物流業界は技術の進化や取り巻く社会的情勢を受けて変化し続けています。中でも、搬送ロボットはその最前線に立つ技術として多くの企業や施設で導入されています。これらのロボットにはさまざまな種類があり、その用途や特性も異なります。
こちらの記事では、それぞれの搬送ロボットがどのようなシーンで最も効果を発揮するのかを解説し、特に注目を集めるAMRの普及が進んだ理由やその特長に焦点を当てて紹介します。
目次
搬送ロボットの普及が進んだ理由
物流現場で活躍する搬送ロボットについて役割や普及が進んだ理由などを詳しく解説します。
搬送ロボットとは
物流倉庫や製品工場では、商品や部品を運ぶ作業が日常的に行われます。従来、このような作業は主に人の手で行われていましたが、人の手での運搬には効率性の問題やミスが発生するリスクが伴います。しかし、近年の「搬送ロボット」の登場により、これらの作業を代替して効率よく実施することが可能となりました。
初期の搬送ロボットは、レーザーや磁気センサーを使って、あらかじめ決められたルートを移動するようにプログラムされていました。しかし、技術の進化により、今ではAIを使ったロボットが開発され、自ら環境を認識して自律的に移動することが可能になりました。
最大の変化は、ロボットが商品や部品だけでなく、商品棚ごと運ぶことができる点です。これにより、人が倉庫内で商品を探しに行く必要がなくなり、ロボットが商品棚を持ってきてくれるようになりました。これは、作業の効率化に大きく貢献しています。
搬送ロボットの普及が進んだ理由
搬送ロボットが普及が進んだ理由はさまざまですが、大きく分けてロボットである事に起因する理由と搬送ロボットならではの理由があります。まず、ロボットである事が起因する理由は、人間よりもはるかに重い荷物を容易に運ぶことができ、これにより大量や重い物の移動が劇的に効率化されます。
また、人が行う作業にはどうしてもエラーやミスが含まれる可能性が高まりますが、ロボットは一度設定されたプログラムに従って正確に動作を繰り返すため、ミスが大幅に減少します。
次に搬送ロボットならではの理由について解説します。搬送ロボットは自動で最適な移動ルートを計算・選択する能力を持っているため、物の移動が人が行うよりも迅速かつ効率的に行われます。
搬送ロボットを導入するためにかかる費用もありますが、ロボットの導入により、人件費を大幅に削減することができ、企業の経費を節約することが可能です。そして、ロボットの計画的な動作は、業務の予定や計画を立てやすくし、全体の業務運営をスムーズに進めることができるのです。
搬送ロボットの種類と活用シーン
搬送ロボットにはさまざまな種類が存在します。代表的な3つ搬送ロボットについて特徴と、どのようなシーンで活用されるのか解説していきます。
AGV
AGVは無人搬送車のことで、磁気のガイドテープをガイドとして自動で走行し、搬送作業を行う機械です。特に重量物の搬送においても、AGVは効率的に取り扱うことができます。ただし、搬送ルートを変更したい場合、磁気テープの再配置や工場のレイアウト変更の検討が必要です。
AGVの特徴でもある大きな積載重量にも対応できる能力は、カゴ車や台車の牽引する際も発揮されます。これにより、一度に多量の商品や製品を効率的に運搬できます。主に工場や倉庫での移動作業に利用され、工場から隣接する倉庫への製品輸送や、倉庫内での入荷品の移動といった場面での使用が一般的です。
使用後は台車をもとの位置に自動で戻すことも可能です。また、AGVは単なる運搬だけでなく、適切な設定を施すことで、仕分け作業なども自動化できます。また、AGVの中には、AMRやGTPなどさまざまなタイプがあり、それぞれの特性や機能が異なります。
AMR
AMRは、協働型の自律搬送ロボットとして知られ、次世代のAGVとも言われます。AGVが磁気テープなどを必要とするのに対し、AMRはセンサーや空間認識技術を使って自らの位置を認識して動きます。
具体的には、レーザーSLAMや画像認識技術などを利用して、倉庫内のレイアウトを把握します。そのため、AGVが固定のルートを走行するのに対して、AMRは状況に応じて自主的にルートを選択します。さらに、導入の初期コストがそれほど高くなく、小規模の施設でも効果を感じやすい点も魅力です。
AMRは特に、取扱う商品が小さく軽いケースや、1つの宛先に出荷する量が比較的少ない場面での活用が見られます。これは、EC(電子商取引)の出荷業務など、多様な商品を少量ずつ出荷するケースでの効果が高いためです。
AMRの真価を発揮するのは「マルチオーダーピッキング」であり、複数の注文を同時にピックアップして集約する作業を効率的にサポートします。さらに、AMRのあらかじめ決められたルートに固定されずに、必要に応じて自由に移動できる特性により、出荷待ちの商品を一時保管エリアに運んだり、誤って取り出された商品を元の棚に戻すといった多岐にわたる作業にも応用が可能です。
GTP
GTPは、商品や荷物を人のところまで運んでくる自動棚搬送ロボットのことを指します。従来、人が歩いて棚まで行って物を取りに行く必要があった作業を、GTPロボットが自動化して効率化します。具体的には、ロボットが指定された地点から別の地点まで、棚自体を運ぶ役割を持っています。
日本国内でも、GTPの導入実績は増えており、特に中規模以上の施設での利用では、導入コストに見合った高い効果が期待されています。このロボットの主要な機能は、作業者のもとへ直接、商品を含む棚全体を運ぶことです。この機能により、作業の簡略化とが実現されます。
さらに、GTPのもう一つの強みは、在庫の自動配置換え機能です。出荷の頻度が高いアイテムの棚を、作業者にとってアクセスしやすい位置に自動的に移動させることができます。この配置換え作業は、入出荷作業が行われていない時間に自動で実施されるため、作業の中断や人手の介入は必要ありません。
AGVからより柔軟性の高いAMRへ
AGVは、1980年代から物流の現場、特に倉庫や工場において重要な役割を果たしてきました。しかし、近年、AMRという新しいタイプのロボットが登場し、物流業界に革命をもたらしています。
AMRはカメラやセンサーを活用して自分の周りの環境を認識し、自らの判断で障害物を避けながら最適なルートを選んで移動します。この柔軟性は、変わりゆく環境や突発的な事象に対応するのに非常に有効です。
最近の社会的背景、特にコロナ禍を受けて、非接触やソーシャルディスタンスのオペレーションが重視されるようになり、AMRのように人との協働が容易な技術が注目されるようになりました。また、AMRは設定や更新が容易で、迅速に変わるニーズや状況に対応できるため、多くの施設や企業がAGVからAMRへの移行を進めています。
搬送ロボットの普及はミスの削減や効率化、作業計画の立てやすさに留まらず、人不足が懸念される物流業界において問題を打開する手立てとしても注目されています。
AMRは、現場の変化に迅速に適応する能力を持ち、人との協働にも優れているため、今後の物流業界における中心的な役割を果たすことが期待されています。
大喜産業では、MiR社のAMRを代理販売しています。詳しくは公式ホームページよりご確認ください。